モデルで説明する楽な心・苦しい心

03-04 人に与える「感情の二次体験」の傾向
二次体験は、過ごした家庭や環境ごとに、特定の傾向を持つところがあり、その傾向に応じた学習が蓄積されることになります。
この蓄積された学習の違いによって、他の人に与える「感情の二次体験」の傾向が、次のように分かれます。
■「予防を強化する二次体験」による学習によって、「『感覚・感情』を隠す性質」を身に付け、「予防を強化する二次体験」を与える傾向が強くなる
■「気持ちを回復する二次体験」による学習によって、「『感覚・感情』を大切にする性質」を身に付け、「気持ちを回復する二次体験」を与える傾向が強くなる
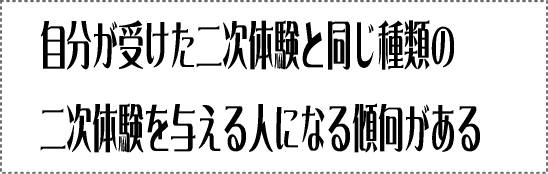
自分の二次体験に関わる人は、このいずれかの傾向を身につけた人たちです。
二次体験の善し悪しは、自分に関わってくれる人が持つ傾向によって決まります。
そして、「自分の二次体験に関わってもらう人」は、自分で選ぶことができます。
ですから、「気持ちを回復する二次体験」を与えてくれる人を選べるので、何の問題もないように思えるのですが、ここに落とし穴が潜んでいます。
「『感覚・感情』を隠す性質」が強い人は、自分と似た性質の人を「自分の二次体験に関わってもらう人」として選びやすいのです。
それは、「『感覚・感情』を隠す性質」を持った人は、「『感覚・感情』を大切にする性質」を持った人に「何だか嘘っぽい」「分かっていない」と感じ、逆に、同じ性質を持った人には「この人は理解してくれる」「この人は分かっている」と感じてしまうことによって起こる現象です。
これは、理屈ではなく感覚の問題なので、避けるのが難しいところがあります。
しかし、ここに注意しなければ、「優しくしてほしい」と願いながらも、いつまで経っても「気持ちが回復する二次体験」を与えてくれる人を遠ざけて、自分の悪いところを指摘するような人ばかりを選び続けてしまう恐れがあります。
